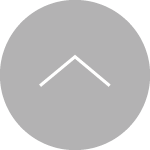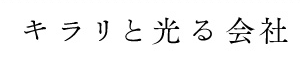

KIGURUMI.BIZ株式会社
KIGURUMI.BIZは、宮崎県にある、その名の通り着ぐるみを製作する会社。社長もスタッフも、ほとんどが女性で構成されています。ものづくりとかわいいものが大好きな女性たちが、丁寧な手仕事でつくり上げる着ぐるみは、キャラクターファンでなくとも、思わず話しかけてしまいそうになる仕上がり。イベントの中止が続いたコロナ禍はKIGURUMI.BIZにとっても大変な試練のときで、社内がモノクロに沈んだそうです。色を取り戻し、これからさらに期待される同社は、働きやすさに取り組み続けてきた職場でもあります。
キラリと光る会社第42回は、KIGURUMI.BIZ代表の加納ひろみさんにお話をお聞きしました。
“ゆるキャラブーム”以来、キャラクターと共に
—着ぐるみを専門にされる前は、ちょっと違う会社だったんですね。
加納さん:造形美術の会社を、夫がやっていました。3Dのものを製作する会社は俗に「造形屋さん」と呼ばれていて、例えば、建築模型とか、舞台のセットなんかもそうですし、同じ看板でも大きな動くカニのがありますよね?あのようなものも造形屋さんが手がけます。着ぐるみも立体物なので、依頼があればつくってました。
—加納さんがその会社を引き継ぐ形で?
加納さん:私も一緒に働いていましたし、夫は私よりひと回り年上なので、私に順番がまわってきた感じで社長を交代しました。もっと遡りますと、私はもともと東京で働いていたのですが、いろんな経緯で福島の奥会津に移って、まちの情報発信に携わっていた時期がありました。当時シングルマザーで、二人の子育て中でした。夫は、そのまちに「人形をつくりませんか」と営業のメールをくれた人だったんです。故郷の宮崎に帰りたかった私は、夫の会社に転職することで戻ってくることができました。その後、職場結婚することになって。
—そうでしたか。では加納さんもしばらく造形美術のお仕事をされてから、着ぐるみを専門でなさることにした。
加納さん:30年前にはいまのような「ご当地キャラ」はいませんし、頻繁ではなかったのですが、ときどき着ぐるみをお客さんに求められました。そんなときは生地屋さんで生地を選んで、手探りで形にしてました。バブルがはじけると、もらっていたいろんな仕事がなくなってしまったのに、着ぐるみだけはぽつぽつと依頼があって、夫と二人だけの会社なのでそれで食べていけたんです。しばらくはそんなふうでした。2008年ごろからのゆるキャラブームで、一気に依頼が増えたんです。
—ゆるキャラブームって、そのころからでしたっけ。
加納さん:2007年に、彦根の「ひこにゃん」が知られるようになって、火がつきました。それから自治体からも発注がくるようになって、数年後に奈良の「せんとくん」、そしてやっぱり、「くまモン」の登場が大きかったです。日本中の自治体がつくりたがるようになりました。
—KIGURUMI.BIZさんの歴史も、キャラクターと共にあるのですね。
加納さん:そうなんです。だんだん、製作の前のデザインや、プロモーションの仕方のご相談までいただくようになって、企画、コンサル的な役割も期待されるようになっていきました。

つくる側の笑顔も大事。
女性が長く働ける職場を
—スタッフの方は、見渡す限りみんな女性ですね。
加納さん:一番多い製作担当は全員女性ですし、全体の9割が女性ですね。
—やっぱり、縫製が得意だとか、ものづくりが好きで入社される方が多いですか。
加納さん:はい。あと、デザインや、かわいいものが好きな人。いい人が多いんですよ。それになぜか、きれいな人が多い。指がきれい、あと、文字がきれい。何より一生懸命やっている姿は、惚れ惚れするほどきれいです。
—素敵。ベタ褒め!いいですねぇ。大事なスタッフですもんね。
加納さん:そうですよ。一人ひとり、みんないないと困ります。
—だから働きやすさ、居心地のよさにも心を砕いてこられたんですよね。
加納さん:みんながここで働き続けられるようにするにはどうしたらいいか、私がというより、みんなで考えてきたんです。お母さんも多いですし、子育て中も働きやすく、続けやすい職場でないといけない。声を上げてもらって、みんなのためになることはすぐに採用、その逆は排除するのが私の仕事です。失敗したり間違えたこともありましたけど、常に考えて、積み重ねてきました。
—特に心がけていることはありますか。
加納さん:みんなが心に置いていることを、なるだけ聞くようにしています。そして、困っていること、やりにくいと感じていることが出てきたら、放置しないようにする。目を逸らさず、なるだけ早く改善、解決策を出して、寝かさずにアクションを起こすよう心がけています。
—あぁ、そうか。「わかったけど、ちょっと待って」と寝かしちゃいがちですもんね。それが待つ側には長く感じられるんですよね。
加納さん:ですよね。
—加納さんは、「正しい商品は正しい場所から生まれる。」と、おっしゃってきたんですよね。
加納さん:私は残業代が支払われないような時代も経験しているので、正しい素材、正しいつくり方、正しい報酬で、うそのないもの、うそのない職場、という思いでそう言っていました。だけど最近、「正しい」って、ちょっと強すぎる言葉だなと考え直して、「こちら側の笑顔と向こう側の笑顔」に置き換えることにしました。良いものをつくるためには、つくる側の心も安定していないといけません。みんながパフォーマンスを発揮しやすい環境を考え続けたいと思います。

どの作業も、驚くほど無駄のない動きでスピーディに進められる。

コロナ禍、職場の景色が色を失う経験を通して
—どんなものもそうですけど、かわいいものは特に、泣きながらつくったものであってほしくないですよね。
加納さん:そうですよね。コロナ禍で、着ぐるみの発注が途絶えて、先も見えなくて、存続すらできるのかと不安になりました。そんな中、医療用の防護ガウンを縫う仕事を請け負ったんですね。2万枚、ひたすら黙々と縫いました。医療従事者の方のための、重要な、必ず役に立つ仕事です。売り上げがない中で、ありがたくもありました。でも、カラフルだったこの場所に色がなくなって、クリエイティブで活気があったはずの職場が、単なる作業場のようになって、みんな、疲弊したんですね。そのときに痛感したんです。世の中にとっていかに大事な仕事でも、誰かのハッピーを犠牲にしてやっちゃいけないって。医療や食糧やインフラのようなものはいうまでもなく大事だけど、ワクワクや癒し、楽しさも大事で、私たちは、その部分を提供することで命を支えるのがミッションなんだって。苦しかった時期を経て、みんな残ってくれて、徐々に、ここに色が戻ってきたのを見て、これからは着ぐるみやキャラクターだけをやっていこうと決めました。
—あぁ、本当に。不要不急とか、エッセンシャルワークとか、そういうのはもっともなんですけど、選別されるのはつらいと思いました。文化や芸術、音楽とか、おっしゃるような癒しとか、楽しさとかも、ないと内面が枯れていくようでした。
加納さん:本当にそう思います。つくる側としても、やっぱり、みんなが笑顔でできる、やりたいことでなければダメだと思いました。
—全然先が見えない時期もありましたから、あの状況では、できる仕事は受けようと考えるのも無理もなかったと思います。
加納さん:私はもう、不安で不安で、コロナ前のような仕事は一切できなくなるかもしれないからと、あらたな種まきばっかりしたんです。その芽がいまいくつか出てきていて、きれいな花を咲かせられるようにがんばっているところです。
—素晴らしいじゃないですか。
加納さん:海外で出た芽もあるんです。以前からおつきあいのあった方が、KIGURUMI.BIZ USAとして、シリコンバレーで窓口になってくださることが決まって。あちらで受けてくれた着ぐるみのお仕事を、日本で形にして送るんです。
—わぁ、それはすごい!楽しみですね。ずいぶん立派な種をまかれて、経営者としてもご立派です。
加納さん:元来弱虫なんですよ。オロオロと石橋を叩くばっかりの性格です。経営者になったからといってまるで変われていないのですが、環境は大きく変わったんですよね。いただいたご縁がそれはそれはたくさんあって、あのときあの人に会っていなければどうなっていたか…っていうことだらけなくらいです。そうした人のご縁に恥じないようやっていかないといけないと思ってます。


KIGURUMI.BIZのWebサイトに並ぶ数々のキャラクター。個性いろいろ、まさにカラフル!
「誰かのために」となったとたん、体が動く!
—御社の、ファンもいっぱいいるのではないですか。
加納さん:ありがたいことに。ご当地キャラが集合するイベントでは、大勢の人の中でケガをしてしまうキャラクターがいるので、うちは“お医者さん”として、応急処置の修理をしたりする形で自主参加していました。いまは呼んでもらえるようになって、親しみを持って接してくださる方も増えました。
—そうかぁ、そういうキャラクターってもう、着ぐるみであってそうではないというか。だからお医者さん。
加納さん:そうなんですよ。キャラクターとして生きているんですよね。キャラクターがつないでくれるご縁もまた少なくないんですよ。東日本大震災のときには、津波で流されてしまったキャラクターもありました。岩手県宮古市の「毛ガニ君」もそのひとつで、つくって1ヶ月くらいで震災に遭って。いたたまれずつくり直してお送りしたんですね。そうしたら、お礼にと、食べられる方の(笑)毛ガニを送ってくださったりして、いまもおつき合いが続いています。キャラクターは、つくって出荷したらおしまいというより、その後の歩みもシェアしてくれるところがあるんです。
—いいですね。楽しいですね。
加納さん:楽しいですよ。扱っている商材が楽しいんですよね。自分たちの提供するものを受け取る人たちが、ニコッとする、笑顔を生むって、うれしいです。結果が楽しいところに行き着く商品をつくるという喜びが、この仕事にはあります。
—このお仕事が本当にお好きなんだなぁっていう方を見ると、こちらもうれしくなります。
加納さん:その実、コロナでズタボロになって、 沼から上がってきたところのような状態なんですけどね(笑)。まずはシャワーを浴びて、お日様に当たって…という段階。
—お日様浴びた後はどうされたいですか。
加納さん:会社を、もっと大きくしたいというのはなくて、もっと喜んでもらえるようにしたいですね。もっといい環境と待遇で、したい仕事ができるように、いい人たちといい関係を保ち続けられるように、ということを考えていきたいです。この、ほんわかした会社が、そうやってずっと続いていくのがいい。
—加納さんご自身についてはどうでしょう。なにか、個人的に実現されたいことなどありますか。
加納さん:私自身はもう、たくさんいただくばかりで、これ以上望めないくらい恵まれていると思っています。私は、言ったように弱虫だし、ひとりではプラスもマイナスもない人間というか、攻めの人生みたいのはなくて、誰かがいるおかげで動く人生なんです。
—誰かがいるおかげで動く。
加納さん:私、「誰かのために」となったとたんに苦じゃなく体が動くんです。会社のため、好きな人たちのためだと急にスイッチがはいる、そういう、少女っぽいところがあるんですよね(笑)。そうやって私を一生懸命にしてくれる人たちがいるから、人生が動くんです。
—そういうことですか。誰かのためにとなったとたんに。
加納さん:自分のためには絶対できませんけど、誰かのためなら徹夜で運転して、どこまでも駆けつけられます。
—そういう人を「いい人」って言うんですよ! KIGURUMI.BIZのスタッフの方は幸せだと思います。
加納さん:そうなんでしょうか。地元での知名度が低いせいなのか、なかなか応募してもらえなくて、人が足りないのが最大の悩みなんです。ものすごく、心から、来てもらいたいです。

加納さんと、自社のキャラクター「BIZ BEAR」♡




2018年入社。社長室室長。前職では英語を教えていたという仁田脇さん、現在は「海外戦略チーム、未来戦略チームを軸に、これからのKIGURUMI.BIZをつくっていく」役割だそうで、諸外国の顧客からの問い合わせ対応や輸出サポート、契約書・知的財産等の法務サポートもされている。加納社長は、社内で「みんな集まってー!」などと集合をかけたり、仕切るのが苦手とのことで(笑)、そんな場面でも頼りにされているとおっしゃっていました。
英語を話せる人を探している会社があると友人が教えてくれて、それがKIGURUMI.BIZでした。仕事の内容は初めてのことが多いのですが、不安よりワクワクが勝って、いまに至ります。社長がワクワクのかたまりのような人で、会社のために常に走っては、いろんなものを持ち帰って来るんです。「明日はどんな話を持って来るんだろう」って思ってます(笑)。KIGURUMI.BIZはつながりを大事にするあったかい職場であると同時に、自分自身を理解しながら学び合える、個々の成長を感じやすい職場だと思います。うちの一番の知的財産は、みんなの技術。私の役割は、先を見て、みんなの世界を開いていけるような仕事をつくることだと思っているので、責任重大ながら努力していきたいです。
編集後記
第40回のそらのまち ≫は、先に取材のお声がけをした加納さんからのご推薦でした。そらのまちの古川さんは、加納さんを「勝手に親友だと思ってます」と、加納さんは古川さんを「私が勝手に大好きなんです」とおっしゃり、まさに相思相愛。お会いしてみれば、このお二人を嫌いな人なんていないだろうと思いました。着ぐるみそのものに関しては、正直さほど興味があったとはいえない我らでしたが、取材後にはもう、そこにある全部が愛らしく、体温を持つものに感じられました。キャラクターという特性上、ほとんど写真に写せなかったのですが、どの工程も、感嘆せざるをえない手際のよさで、パーツごとに、手で命を宿していくようでした。海外の人たちにもこのあたたかさが伝わりますよう、素敵な人たちからのスタッフへの応募がありますよう、「KIGURUMI.BIZに幸あれ」などと、勝手に願っています。(2023年11月取材)