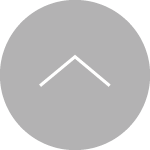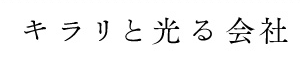

加計呂麻バス有限会社
奄美大島からフェリーでほんの20分ほど、『男はつらいよ』の有名ロケ地でもある加計呂麻島の港に到着すると、朱色とクリーム色を基調に、草色を効かせたストライプ、なんともレトロな加計呂麻バスが待っています。奄美群島の人口1200人あまりの島で、昭和55年以来運行を続ける加計呂麻バスが運ぶのは乗客だけではありません。ものを運び、新聞を配り、お年寄りの乗降を手助けします。だんだんと、これが最先端かもしれないと思わせるその姿。時代に翻弄されながらも、島の物語を乗せて、今日ものどかな道を行きます。
キラリと光る会社第24回は、加計呂麻バス代表の林健二さんにお話をお聞きしました。
昭和55年、
「運転手さん」ではなく「船長さん」と呼ばれた
—昭和55年ですから、40年ほど前に運行を開始したんですよね。
健二さん:そうですね。当時は、たまたま名前が同じ、林バス産業という、奄美大島に本社を置く会社でした。そこでバスの運転手をしていた親父が、加計呂麻営業所ができたと同時に所長になって、こっちに移ってきたんです。島唯一の公共の陸上交通機関。僕が2歳のときでした。
—では、林さんご一家は、加計呂麻島ご出身ではないのですか。
健二さん:母方の祖母、父方の祖父が加計呂麻です。僕らは奄美大島ですけど、だからルーツはありますね。
—そうでしたか。移っていらしたときから比べて、島は変わりましたか?
健二さん:当時の人口は4900人くらいだったから、いまの4倍いました。でも道路の舗装もまだほとんどされていない状態。島の人はバスなんか見たこともなくて、「運転手」という言葉も知らなかったそうですよ。「船長さん」「機関長さん」なんて呼ばれたと聞いています。鍬(くわ)とか持った乗客が乗ってくるバスでした。
—おお…。バス自体をご覧になったことがなかったのかぁ。船の方が馴染み深くて「船長さん」というのも、島ならではですね。
健二さん:そうなんですよ。バスの整備もパンク直しも運転手が全部自分たちでやって走らせてたんですよね。ちなみにそれはいまも変わりません。
—すごい。普通の乗用車とは違いますもんね。
健二さん:そうそう。そのうちなんでも自分たちでできるようになって、補修も板金屋さんに出したことがない。廃車にするときには使える部品を取り出して、なにかのときに再利用したりもしてます。
—わー、すごいなぁ。
健二さん:親父が口癖のように、バス会社は補助金もらってるから、1円も無駄にできないんだって。17年間で70万キロ走ってる車輌もありますね。

ヤギにエサをあげ、救急車にもなるバス
—健二さんは、若いころから自分もバス会社に関わりたかったのですか。
健二さん:いやいや、ぜんぜん!Uターンする前は、大阪で建築設備のエンジニアをしてました。彼女もいたし、まだ20代の前半ですもん、帰る気ゼロでしたよ(笑)。都会を謳歌してたとき、親父に帰って来いと言われて嫌々です。
—それはそれは(笑)。でも、息子さんの力を借りたかったんですね。
健二さん:その割に帰ったら仕事ないんですよ(笑)。どうしようかと思いましたね。テレビもない、ラジオもない、マックのドライブスルーも見たことねぇ!って、なんかの歌みたいなところでしょ?いつかは帰らねばとは思ってたけど、それにしてはまだ若かったから。
—あはは。それでもい続けたということは、そのなにもない中になにかを見つけられた、ということですかね。
健二さん:そうなんですかね。ずっと親父の背中見て育ちましたからね。「人的バリアフリー」って言ってるんですけど、バスを乗り降りするお年寄りの手を引く姿とか。不便な島なので、バスで新聞配達して、寿司でもケーキでも、あと給食も運びましたし、買い物はもちろん、頼まれればヤギのエサをあげたり、その昔は印鑑と通帳預かって郵便局でお金おろす代行までやってましたよ。
—えええ!ヤギ?通帳!?
健二さん:びっくりですよね(笑)。いまと違って昔は他人の通帳と印鑑持参したらお金おろせましたから、「2万円おろしてきて」なんて、信用して預ける人もいたんです。会社のバスはときに救急車代わりにもなってましたし、島では個人で船を持ってる人が珍しくないんで、親父なんか自分の船出して急病人を奄美大島まで運んでましたよ。
—それはもう完全に、私たちの思うところのバスの運転手さんを超越したお助けマン!スーパーマンですね。
健二さん:島ならではですよね。でもそうやって、とにかく人の役に立とうとしていた。いまでこそそんな親父のことを尊敬してますけど、思春期には、正直恥ずかしいと思ったこともありましたね。
—思春期あるあるですよね。いや…、感動します。

手前の笑顔の方は古参の運転手さん。バスの終点で乗客を降ろすと、すぐそばのご実家から魚肉ソーセージを手にして戻り、慣れた手つきでウナギにあげ始めた。島時間の、ほのぼのした光景。この川には大きなウナギがいっぱいで、ちょっとした餌付けショーのよう。ここから少し歩くと海に出て、そこにはウミガメの姿も。身近な自然の豊かさにも驚かされる。
地域活動の延長で、親子で地方議員も経験
健二さん:平成14年に、前身だった奄美大島の運行会社が倒産して、加計呂麻が再びバスのない島になるところだったんですよ。そのとき親父含め10人のバス運転手が、借金してあらたに別の会社をつくって存続させたんです。
—借金してバスを…。それはずいぶんと思い切りましたね。運転手さんたちが団結できたのもすごいです。
健二さん:島の人に役立ってる実感があったんでしょうね。実際、なくなると住民の方々は困ったと思うんです。そのあと33集落すべてから感謝状もらってました。いまも励みしています。
—そうですか。いいお話ですね。
健二さん:親父は、そうやって公私ともに地域のために活動してたら声がかかって、政治家なんか嫌いだと言いながら出身地・奄美大島の瀬戸内町の町議に担がれて。ずっと、誰かのためにとやってきた人ですね。
—町議に。慕われていたんですね。
健二さん:親父がそんなだったから、僕もバトンを渡されるように町議をやりました。最初ははただ、「若手がいない」という理由で推されたんですけどね(笑)、僕なりにやってみて、行政でできることも多いと思いました。過疎地の代表みたいな地域を知る者の声も必要だと、そのあと県議も務めました。
—島に帰る気ゼロだった若者が立派になったんですね(笑)。
健二さん:あはは。自分自身、気持ちが変わっていきましたよね。

健二さんのお父上である会長さん(左)の近年の趣味は、写真を中心にいろんなものをラミネートすることとテプラだそう(笑)。この趣味は、健二さんや、やはり加計呂麻バスで働く娘さんに、笑われながらもあたたかく見守られている。
厳しい経営環境。
この島ならではの観光のあり方を探る
—お年寄りの足として、島の生活物資の運搬手段として、加計呂麻バスさんはいまも必要とされているのは確かだと思うのですが、人口減が止まらない中での経営は大変なのでは。
健二さん:おっしゃる通りです。路線バスとしてだけではどうにもならないので、団体の受け入れをして貸切の観光バスも走らせています。路線バスと貸切バスでは別の許可が必要で、両方やってるのは全国的にうちくらい。だから業界では知られているんですよ。
—静かな島ですが、いまも根強いファンの多い『男はつらいよ』の有名なロケ地ですし、なによりこの環境が観光資源ですもんね。
健二さん:山田洋次監督は、加計呂麻への思い入れが深いようで、撮影から四半世紀を過ぎたいまも島を訪れてくれています。うれしいですね。
—それはうれしいですね。でも、この島に思い入れが深いというのは、なんとなくわかる気がします。
健二さん:渥美清さんが病気を押して撮影に臨んでいらっしゃいましたしね…。
—ですよね。
健二さん:『男はつらいよ』の撮影風景は、高校生だった僕も目にしています。あのころ僕は親父の船で通学してたんですよ。中3で免許とって、自分で操舵して、奄美大島の高校に通ってました。
—ええっ、船通学ですか!?
健二さん:よその人はみんなびっくりするんですけど(笑)。自転車とかバイク通学みたいな感じ?ここはそんな場所なんですよ。
—それはバスの運転手さんも「船長さん」と呼ばれるわけですね。
健二さん:あはは。10年くらい前、NHKの『にっぽん紀行』で取り上げてもらったことがあるんです。地域密着の人にやさしいバス会社の経営が危機に直面しているという。運転手がお年寄りの乗降を手助けするシーンや、自ら観光ガイドをするシーンが映し出されました。あのときは反響が大きくて、全国から、「がんばって続けてください!」という励ましのお手紙や、お金まで送られてきました。
—お金まで!よほど心に響いたのでしょうね。
健二さん:番組を通して、うちが古いバスを走らせているのを見たからでしょうね、バス会社さんから中古車輌の提供のお申し出もありました。とてもありがたかったのですが、サイズが大きすぎて島の細い道は走れないのでお受けできませんでした。
—あたたかい人たちには、あたたかい思いが集まるのですね。
健二さん:そうなんですかね。たくさんのご厚意を受けてなんとかやってます。近年は特に、加計呂麻が注目されている実感があって、うちも大手旅行代理店とも契約しましたし、地域密着は維持しながら、都会にはない観光の姿をさらに探っていきたいと考えています。
—乗らせてもらいましたけど、ここで路線バスに乗るだけでも十分、体験型の観光というか。都会にないのはもちろんなんですが、外から来ると、ここの日常に、私たちがなるだけ邪魔にならないように触れさせてもらえれば、それがなによりの思い出になると思いました。その思い出の風景には、加計呂麻バスがいる。
健二さん:僕らにとっては当たり前すぎてわからないことばっかりなんですよね。ずっと、なにもない島だと思ってて、ましてやお金にかえられるようなものは持ってないと。都会の人がお金を払ってでも見たい、やりたいということに対して、「そんなものにお金払ってもらっていいんだろうか」という躊躇が、島の人間には常にあるんです。そのあたりを、もう少しきちんとわかるようになって、双方にとって良い形の観光なりを生み出していけたらと思っています。

全国から届いたお便りは、大切に保管されている。

息子さんと娘さんにはさまれて、両手でピースの会長さん。



前身の林バス産業(お名前が同じなのは偶然で親戚関係等ではない)に、バスの運転手として入社。加計呂麻に支店ができた際に所長として赴任し、会社が倒産したとき、ほかの運転手と共に事業を引き継ぐ形で現在の加計呂麻バスを設立する。人に尽くす立派な方であると同時に、話していて楽しい大変お茶目なお人柄。
私は、昭和22年生まれ。当時奄美はアメリカの統治下※だったから、アメリカ生まれですよ。日本との行き来にはパスポートが必要だった。私たちは英語のしゃべれない変な外人なんです。奄美の歴史はあっちにこっちに支配されてばかり。
昭和30年代に上京して、タクシーの運転手をしました。基本料金は100円でしたよ。怖いお客さんもいてね、島に帰りたくなって、Uターン後にバスの運転手になりました。いまはお客さんの命をあずかる者の誇りとして、「運転士」って言ってます。地域のみなさんのお役に立てることが、なによりのやりがいですね。息子には、ふるさとは遠きにありて思うものではなく、住んで興すものだと言って帰ってきてもらいました。娘は三味線ひいて唄うので、ダンナに運転してもらいながら夫婦バスやったらいいってすすめるんですけどね、まだ若いから恥ずかしがってイヤだって言うんですよ(笑)。
※ 奄美群島が返還され本土に復帰したのは昭和28(1953)年12月25日。
編集後記
(奄美ではかなり知られた人物ではありますが)人知れず立派なことを為している方がいるものです。加計呂麻バスが地域にしてきたことを前にすると、「カスタマーファースト」なんて言葉が空虚に感じられます。たくさんご苦労もあったでしょうが、会長さんはほのぼのとしていて、自らが語る通り、人に役に立てることが、純粋にうれしかったんだなぁと。奄美の歴史と考え合わせては、なんとも胸にくるものがありました。息子である健二さんは、そんな会長さんのお話が止まらなくなっても、遮ったり茶化したりすることがなく、何度となくお聞きになっているであろうお話も、横でうんうんと微笑みながら。そこにある信頼と愛情は、初対面の私たちにも感じ取れ、やさしい気持ちが伝染しました。キラキラと光る、ウミガメが泳ぐ海とレトロなバス。ちょっと夢みたいでした。(2019年11月取材)