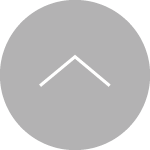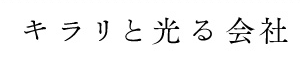

株式会社ケンランド
創業1948年、山形県山形市のニットメーカー。社名は創業者の大沼健蔵さんのお名前から。山形県はニットの産地として知られ、ピークの1980年くらいまでは800〜1,000の業界企業が存在していたものの、現在は50社あまりとなっているそう。ケンランドは長くOEMの会社として操業し、多いときには130人の従業員を抱えた会社。父親から会社を引き継いだ大沼秀一社長が、試行錯誤を重ねながらリネンの製品づくりを本格化させ、2010年に自社ブランド「KENLAND LINEN」を立ち上げました。20人弱のスタッフが、素材選びから製造、販売までを一貫して行なっています。
キラリと光る会社第23回は、ケンランド代表の大沼秀一さんにお話をお聞きしました。
ニットの産地・山形で、
「こうあるべき」を気にせずに
—まず基本的なところを。ケンランドさんはリネンのニットを製造、販売していらっしゃいますが、その、私たちが何気に「ニット」と呼んでいるものは、具体的にはなんなのかあらためて教えてください。
大沼さん:多くの衣服は“織物”でできています。ファブリックともいいます。縦糸と横糸を交差させて面をつくり、張りのある生地になります。ニットとはつくり方がまったく異なります。ニットはいわゆる“編物”。一本の糸をループ状に絡ませる工程を繰り返して編み上げます。リネンのニットは製造がむずかしいんです。分離していく性質があるのと、スレにあまり強いとはいえず、つくる側としては非常にリスクが高い。それでも、やわらかで風合いがよく肌に馴染みやすい、それに気温の変化に柔軟な繊維で、余りある魅力と機能性を持ち合わせています。
—そうか、ファブリックに対してニット。織物と編物。ニットは一本の糸から完成させるんですね。ケンランドさんは、創業時からニットを製造していらっしゃったそうですが、山形がニットの産地だったことは知りませんでした…。
大沼さん:いまは知らない人のほうが多いですよね。福島や新潟も盛んだったんですよ。ただ、ニットはもともと都市型産業で、東京や大阪で製造していたのが手狭になったため、それらの地方に工場を移していったんです。ところが山形は成り立ちが違います。自然発生的なんですよ。
—なぜ山形だけ?
大沼さん:羊を飼う農家が多かったので糸があったんですよ。加えて編機を製造する会社もあった。染色も盛んでした。
—なるほど、条件がそろっていたんですね。
大沼さん:それに山形の人は、自ら都会でお客さんを開拓して歩いた。東京はもちろん、ニューヨーク、パリ、ミラノと。そんな産地はほかにはなかったんですよ。気質なんですかね。
—そうなんですか。知られざる山形県民気質!
大沼さん:50年くらい前の全盛時には、この産業も活気がありましたよ。いまは50社ほどになった県内のニット関連の会社が、当時は1,000社ほどもあって、潤ってましたね。
—1,000社もありましたか。大沼さんもそんな会社のひとつの、おぼっちゃまだったんではないですか(笑)。
大沼さん:そうですね、その時代は裕福でしたね。高校から東京に出ましたし、よく遊びましたよね(笑)。賭け事なんかも学生時代にやり切ったな。
—なんと!(笑)
大沼さん:でもこの産業自体が下り坂になってきて。うちも一時はヨーロッパや中国でも仕事をしましたけどね、僕もずいぶん、個人のお金を失うようなこともありましたよ。だまされたりしてね。
—だまされた!
大沼さん:まぁ、いろいろ失敗はありますよ。でも、親から受け継いだものを守ろうという考えは、当時もいまもあまりないんです。山形のなにかを守ろうというのはさらにないタイプ。だから思い切ってできたんじゃないかな。
—あはは。それを公言する経営者の方は珍しいかも(笑)。
大沼さん:業界のセオリーみたいなものも、ほとんど気にしませんしね。「こうあるべき」みたいなものはないんですよ。結果として機能すればいいと思ってる。でも、原料の畑にまで赴くのはうちくらいですし、特に自然環境の側面から、持続可能なものづくりについては、常に意識してきました。
—こだわるポイントが違うということですかね。

リネンという、知られざるやっかいな素材
大沼さん:うちは、全国の百貨店での催事販売をメインにやっていて、百貨店さんとおつき合いが密だけど、百貨店の思う「きれいなもの」を目指してはいないし、特別高価なものもつくってない。なにより、頼んでもいつあがるかわからないようなメーカーです。スキマで商売してます。
—いつあがるかわからないというのはすごいですね(笑)。
大沼さん:リネンというのは、ニットの素材として、相当むずかしいんですよ。いくら厳選した糸を仕入れても、そのときどきのムラがあって、毎年どころか毎日、同じものができるとは限らないんです。70〜80%の湿度が適していて、暖房に弱く、デリケートでもあります。乾燥すると編めません。歩留まりが悪くて3割はダメです。
—えええ…。そんなにやっかいな素材なんですか。
大沼さん:自然のものだとはいえ、栽培の段階でデキがいいのは4年に1度くらいですからね。ヨーロッパから入ってくる原料にムラはありますよ。それでも仕入れ先にクレームつけたことはありません。相手との共存という意識もありますし、そもそも買って編んでみないとわからないんです。編んでみて、できるものをつくるということですね。
—それはちょっとびっくりです…。では、「去年と同じものを」という注文も、かなえられないときがあるということですか。
大沼さん:そうそう。すごいでしょう(笑)。
—いまのご商売を成り立たせてきたケンランドさん、ご立派ですね…。
大沼さん:当初は糸を手にすることはおろか必要な情報を入手することもできませんでした。ヨーロッパに出向いても相手にしてもらえなくて。それでも通いつめて。
—そうまでしてなぜヨーロッパだったんですか?国産という選択肢はなかったのでしょうか。
大沼さん:同じ麻でも日本の麻は、昔から多くは大麻=ヘンプ(Hemp)なんです。これはどこにでもできる植物です。うちが主に使うのは亜麻=フラックス(Flax)で、これがリネン(Linen)の原料になります。フラックスの栽培は、フランスのノルマンディーを中心とする北緯49度以北の海岸線が適地とされていて、日本ではむずかしい。ヘンプ、フラックスのほか、近似種で主なところでは苧麻(ちょま)=ラミー(Ramie)があります。ヨーロッパではフラックスを原料としたもののみを「リネン」と呼ぶんです。ところが日本では一般に、全部一緒くたにして「麻」とと呼ばれているのでややこしいんですよ。
—おお。確かに、どれも名前は知っていましたけど、ひっくるめて、麻、リネンと呼ぶものだと思ってました。おっしゃる通り、ややこしい…。
大沼さん:繊維としての機能は似てはいますが、大麻はアサ科、亜麻はアマ科、苧麻はイラクサ科と、それぞれ異なる植物からできています。どれも歴史があって、遣隋使のころから、日本の帆船は大麻でできていましたし、神事の際の衣も大麻でつくられていました。捨てるところのない優れた素材で、うちも一部の製品に使っています。亜麻が日本に入ってきたのは明治になってからです。大麻よりしなやかな布になります。最近だと、亜麻の種から得られる亜麻仁油が、健康志向の人たちに注目を浴びていますね。苧麻も、伝統的な織物で使われてきました。奈良や新潟の上布(じょうふ)はこれからできています。
—なるほど、日本でも麻自体は古くから利用されていましたもんね。けれど、ケンランドさんが主に使う「リネン」については、ヨーロッパから調達する必要があるんですね。

糸の状態のリネンは想像よりもうんと手触りがソフト。
ほかはやらないことをやっている
大沼さん:そうです。それにリネンの使い道として、衣服というのは実はマイナーなんです。例えば車の内装に用いるプラスチック素材や、自転車のフレーム、スキーの板、テニスのラケット、ドル紙幣にも入ってます。驚くほどいろんな素材に配合されてるんですよ。強度があるので、軍服やロープみたいな軍用にも多用されてきましたし、要するに使い道がいっぱいあるから、努力しなくても売れる素材なんです。それもあってなんです。
—ぜんぜん知りませんでした。知らないことばかりです。
大沼さん:もちろん、衣服にしても優れているんですよ。夏のイメージが強いのは、赤外線であたたまらない素材だから、熱がこもらず涼しいからです。汗を逃すし菌は繁殖しないし、臭いの元をつくらないという特性もあります。体温に対してバランスがいいので、実は寒い季節にもとてもいいんですよ。
—大好きです。着慣れると手放せなくなりますよね。それにしても御社ではずいぶん細かく商品開発をしていらっしゃるんですね。
大沼さん:自然とこうなりました。つくるほうも同じのばかりじゃ飽きるでしょ(笑)。時代に合わせた設備でもないのですけど、野放図にそろえていったから、ほかにはない変わった機械があったりして、いろんなものをつくれるという事情もあります。ヨーロッパのバイヤーにも、うちみたいな仕立ての仕方は見たことがないと言われますよ。
—色もたくさんあって、きれいです。
大沼さん:色彩については、僕がかなり深く学びました。ストールやソックス、アンダーウェアはこれまでに100色以上、毎月5〜10の新色をつくり続けています。流行は認識しつつもあまりこだわらず。
—すごい色数ですね!染色も、県内の会社さんなんですよね
大沼さん:はい。複雑な染色手法であることもあって、もうそこでしかやってもらえないんですよ。
—つまりは、なにからなにまで、ほかではできない製品しかつくっていないということですね。
大沼さん:やる気になればできるでしょうけど、やらないでしょうね(笑)。うちもいまだ、トライアル&エラーですから。常に、やりながら見つけてゆく作り方、売り方を通しています。
—確かに、いろんな意味で参入障壁高そうですもんね。お話をお聞きしていると、リネンのニットを選んで継続していること自体が、勇気のある経営ですよね。

麻製品の色と言えば…のイメージを覆す、鮮やかなカラーが並ぶ。
自然に逆らわないあり方を探しながらの
ものづくりを
大沼さん:リネンのみにしぼったのはここ十数年のことです。なかなか食べられるまでになりませんでしたからね。
—多品種少量生産で、主に販売されているのは、百貨店での催事。
大沼さん:卸はしたくないんです。セールもないしね。延べにすると年間600日以上、つまりは掛け持ちで、各地の百貨店の催事。僕のスケジュールは1月2日の朝9時から12月31日の18時まで、ほぼ決まってます。
—それもまたすごいですね。では年中、直接お客さんに接してらっしゃるんですね。
大沼さん:そうですね。不思議なもので、すごく売れるときもあれば、まるで売れないときもあります。
—そういう話は聞きますね。「お客さんがみんな相談してるみたいだ」って。
大沼さん:そうそう。びっくりするほど売れたかと思えば、びっくりするほど売れない日もある。それに限らず、長く商売やってれば、ダメなときもありましたよ。でも、まったくダメだったときはありません。一つでも二つでも光がありましたね。
—この先の夢や目標みたいなものはありますか。
大沼さん:そういうことは言わないできました。自然に逆らわないものづくりのあり方を考えてゆきたいですし、無駄なものは買ってもらいたくない。ケアをしながら、補修もしながら、長く長く使ってもらえるものをつくってゆきたいです。

20代の若手も有する職場。みなさんキビキビと働いていた。

山形市に、工場と事務所に加え、多種多様な製品が並ぶショールームも。



工場生産管理担当の結城さんの約35年を筆頭に、社歴30年を数えるベテラン女性陣。村形さんは催事商品デリバリーを、半田さんは総務を担当。「社長よりお客さんに褒められるほうが断然うれしい!」と、笑顔で言い切るステキなみなさんです!(左から、半田さん、村形さん、結城さん)
半田さん:私たちは全員、「事務」で採用されたはずがどんどん広がって、いま事務らしいことをしているのは私だけです(笑)。私は普段売り場に立つことはありませんが、問い合わせなどの機会に、お客さんに製品を褒められるとうれしくなります。一つひとつの仕事に責任を持ってやれる自分に満足感があります!
村形さん:前職でも繊維関係の会社にいました。業界が好きなんですね。山形で作った商品を店頭に送り、直接お客様の反応を聞けることで楽しく働いています。社長から信頼されて任せてもらえることにも、一生懸命やるだけ喜ばれることにも、やりがいを感じています。社内のコミュニケーションはばっちりです!
結城さん:昭和58年入社です。ものづくりも洋服も好きです。だから続けられたのだと思いますが、子育てのときに融通を利かせてくれた職場だったというのも大きいですね。自分で考えて自分で動かないと進まないので主体性が必要ですが、それがやりがいにつながっていると思います。
編集後記
夏は麻素材ばかり身につけているほどですが、それらのほとんどが織物であると認識したことはありませんでした。リネン、ヘンプ、ラミーも、はっきりとは区別がついていませんでした。こうして私たちは、身につけるもの、口に入れるもの、身近なさまざまなものの成り立ちを知らずして、「お気に入り」などと言っているのですね。またチコちゃんに叱られそうです。ケンランドさんのことは、たまたま都内の某大手百貨店で知りました。「山形で」と、少々意外に思ったのも、かの地がニットの産地であったと知らなかったから。それにしても、リネンのニットをつくるのがこれほどまでにむずかしいとは。買い求めた数点のKENLAND製品、これからは胸を張って、「お気に入り」と自慢します。(2019年10月取材)