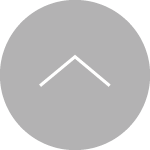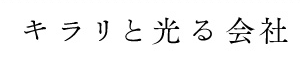

株式会社村田染工

創業昭和26年。創業者は小学校を卒業後、丁稚奉公で染めの技術を身につけて独立。戦後の復興期、毛布を染めたり、着物を染め替えたりする仕事が多かったそう。時代が移り、地域に数十軒あった染め物屋のほとんどが廃業する中、草木染めに活路を見出し、その工業量産化に挑んだのが三代目。化学染料では再現の難しい、深いニュアンスを持つ色彩は、千利休が茶の湯に用いた地下水を使い、今では珍しくなった自然乾燥によって染め上げられます。勤続63年を筆頭に、ベテラン揃いの職人勢、近年若手も加わって、まだまだ攻めるという村田染工。あのエルメスから声が掛かかったことも。
キラリと光る会社第11回は、村田染工の村田正明社長にお話をお聞きしました。
京で、染めの道一筋
—創業なさったのはお父様で、二代目はお兄様、村田社長は三代目にあたるのですね。
村田社長:そうです。父親は滋賀の出身ですが小学校を卒業後、京都の染工に丁稚として奉公に上がりました。独立創業したのは昭和26年。戦時中に倒されたままになっていた木製の電信柱を薪にして、釜で染めていたそうです。私が18歳の頃、この4階建の新社屋ができて、当時は高いビルに見えましたねぇ。ふたりで会社を継ごうと、兄も私も工業高校の染色化学科を出ました。
—子どもの頃からまっしぐらですか。
村田社長:そうですね。高校で学んでいるときから、染色は、なかなか思い通りにならないところがおもしろいと感じていました。19歳で入社して、いい思いをしたこともありますし、苦しかった時期もありましたけど、飽きたことはないですね。
—まず、「いい思い」は、どんなものでしたでしょう。
村田社長:業界では、「60年に1度のムラサキブーム」というのがありまして、それを私は20代の前半で経験しました。布団、座布団、ちゃんちゃんこ、すべてムラサキ色。とにかくムラサキ色の注文ばかりがじゃんじゃんくるんです。そのあとは平成に入ってからのニュー着物のブーム。中森明菜が大ヒット曲「DESIRE」で衣装にしたんですよね。そのブームもすごくて、ほぼ1年中、毎日残業ばかりしていました。私たちの二大繁盛期です。
—そうした繁盛期もあれば…。
村田社長:そうそう、京都の染めといえば着物でしょ。でも、時代が変わって仕事が少なくなって、廃業したところのほうが多いですよ。うちだってもういよいよダメかと思うときもありました。

「新しいことに挑戦するのが楽しい」という村田社長。IT企業など、まったくの異業種の人たちと交流するのも、刺激になって好きなのだそう。
草木染めに出会い、
時代の転換期を乗り越えられた
—だけど切り抜けられた。
村田社長:運が良かったですね。着物の染めの注文が次第に小口になってきて、切り替えを模索する中で草木染めに出会うことができた。
—それまではずっと化学染料で?
村田社長:そうです。以前は草木染めを、趣味や工芸の領域のものとしか見ていませんでしたから、まったく新たな挑戦でした。きっかけとなったのは、正倉院に納められていた真っ赤な靴下を雑誌で目にしたことです。1200年も前のものなのに、今もって鮮やかとしか言いようのない赤でした。その時代ですから当然草木染め。これはすごいと衝撃を受けまして、なんとか工業量産化できないものかと技術の開発に着手したのが平成15年のことでした。ちょうど公的機関などと三者恊働が実現して、草木染めであっても一定の色調を再現できるよう、ひとつ一つ丁寧にデータをとってゆきました。その作業だけで1年半かかりましたね。
—確かに、草木染めといえば、手工芸品の印象がありますね。村田染工さんのそれは、かなり色にバリエーションがありますし、なかなか真似のできない技術なのでしょうか。
村田社長:工業用の草木染めという意味では、胸を張って日本一と言えます。他社が同じようにやろうと思っても、途中で匙を投げるほどにノウハウを蓄積していますから。すべて数値化したことで、基本的には匠の技術がなくてもできるような体制にあります。ただ、原料が自然のものである以上、そのときどきで色の出かたが微妙に異なりますし、素材との組み合わせによっても調整が必要で、機械的にできるようなものではありません。色というのは本当に多様で、赤は赤でも数知れずさまざまな赤があるものです。発注元の指定の色に合わせるのは、なかなか骨が折れるんです。
—そうですよね…。草木染めの仕事を依頼するメーカーさんは、こだわりが強いでしょうし。
村田社長:そうなんですよ。最初に声をかけてくれたのは著名なスタイリストで、ファッションブランドのディレクションも手がけているソニアパークさんでした。私が見て衝撃を受けた、正倉院の赤い靴下が掲載された雑誌を、彼女も見ていたんです。彼女の依頼で、あの靴下の赤をつくり出して洋服を染めました。その後いろんな仕事をいただくようになって、エルメスの、カシミアのストールを染めたこともあります。厳密なエルメスオレンジを草木染めで出すのには、かなり苦労しましたね。
—そのような依頼が指名でくるとは、草木染めにそれだけ魅力があるということですし、やはり、村田染工さんでなくてはならない理由があるからですよね。
村田社長:草木染めの深い味わいや豊かさには、独特の魅力がありますからね。うちが染めに使っているこの地域の地下水は、その昔、千利休が茶の湯に用いた名水で、この水がまた、染めに非常に適した水質で、草木染めのように複雑な色味を呈するものにこそ、真価が発揮されるのかもしれません。それからもうひとつ。村田染工の特徴は、乾燥のしかたにもあるのです。染色後に専用の部屋で自然乾燥させるのですが、こうすることで風合いがぜんぜん違ってくるのです。
—すごい!千利休のお茶にも使われていたとは、さすが京都の歴史を感じます。乾燥方法については、自然乾燥が差別化になるならば、通常は人工的に乾燥させるということですよね。
村田社長:今どきうちのような効率の悪い乾燥方法をとっているところはまずないですね。どこも強制的に、一気に乾燥させます。そうでもしなければ、一般的な量産には追いつきません。ところがうちにくる仕事は、いわゆる大量生産品とは一線を画すものの染めがほとんどなので、自然乾燥だからこその風合いがまた、差別化になるのです。

ここが乾燥室。竹の棒に塩ビをコーティングした物干竿は熱を持たず、染めの色むらが生じにくい。鮮やかな赤は、カイガラムシ由来のラックダイと、薬用植物としても知られるクスノハガシワで染められた。
社長の意識改革が、スタートライン
—独自のものを持って、指名で仕事がくるというのは、職人さんたちにとってもやりがいがあるように思いますが、会社として大きな変化を受け入れて、新しい事業の柱をつくるまで、従業員の皆さんは、すんなりついてきてくれましたか。
村田社長:いやいや、時間がかかりましたよ。まず、草木染めの工業量産化に向けての開発段階で、数値化してデータにするのは「絶対無理」と職人から言われました。なにしろみんな、先輩から教わらずに「盗め」と言われてきた、職人としての勘でやってきた人間ばかりでしょう。私は私で、「じゃあ、(自分だけのノウハウを)墓場まで持って行くのか!」って言い返したりしてね。
—あぁ…、そこは本当に難しそうです。
村田社長:私はもともと新しいことに挑戦するのを楽しいと思うタイプです。すごく負けず嫌いでもあります。だから最初から無理とは決して言わない。とはいえ、従業員にやってもらわないことには、ひとりでなにができるわけではありません。時代の流れで従来の商売が難しくなっていたこともありましたけれど、会社が大変になったのには、私にも原因があったんですよ。周囲の言うことになかなか聞く耳を持てなくて。社長になってから、ある人に、「そんな考え方じゃダメだ!」と厳しく言われたことを境に、変わろうと自分なりに努力しました。
—人間、年齢を重ねるごとに、自分を変えるのが難しくなりますよね。ましてや村田社長は跡継ぎでいらっしゃったからプライドも…。
村田社長:最終的には、ゼロからのスタートなんだと腹をくくって気持ちを入れ替えました。そうしたら、自分のしょうもないプライドなんて捨てたほうが楽だと思えたんです。だって、三代目で会社が途絶えてしまったら、これまで築き上げてきた信頼も、ここだけの技術も、全部絶やしてしまうことになる。和装の伝統文化の一端を担っている責任だってありますし、それらのほうがずっと重大ですよね。
—理屈ではわかっていても、お気持ちを切り替えるのに時間はかかりませんでしたか。
村田社長:叱ってくれたのは、今も当社の技術顧問をお願いしている社外の人で、ご自身も経営者です。この人のところに毎週日曜に、1年間通い続けました。営業のこと、人材育成のこと、工場の設備のこと、とにかくなんでも相談しました。なんでここまで言われないといけないのかと思うくらいに叱責もされましたけど、おかげで意識改革ができました。この人がいてくれなかったら、今の私も、会社もなかったと思っています。私にとってはまさに第二の父です。
—毎週…。そうですか、素晴らしい方と素晴らしい出会いがおありだったのですね。ご自身が変わったことで、社内にも変化が起きましたか。
村田社長:変わったと思います。従業員と私の間にあった壁が、少なからず取り払われたというのでしょうか。以前は私が近づくだけで、「また社長になんか言われる」と、引くような空気があったのが、今は提案などで、あちらからやって来ます。まずはトップが変わらないといけないというのは本当ですね。それから、営業と現場の一体感が業績につながるのだと、身をもって知りました。

草木染めのTシャツがお似合いでかっこいい。いろんな色を持っていて、「その日の気分で選ぶ」のだそう。もちろんご自分たちで染めたもの。
自社オリジナルの
Made in Kyotoを販売するのが夢
—その一体感を生み出すために、どのようなことを心がけていらっしゃいますか。
村田社長:まず、コミュニケーションを大事にするようにしています。皆にとって大切なことは皆が納得できるよう、全社会議で話し合って決めることが多いです。うちは冬期、土曜日も出勤なんですよ。その代わり、特に工場内の温度が高くなる夏は4時半を退社時間としています。祇園祭のあたりは一斉連続休暇も取ります。これも話し合って決めました。それから、頑張りには、目に見える形で応えること。稼いだ分も、節電して浮いた分も、従業員に還元します。決算のときは、心ばかりですがパートさんにも寸志を支給しました。結局、やるのは生身の人間だということですよね。お互いに気持ちが肝心。
—村田染工さんは、これからもさらに良くなってゆきそうです。
村田社長:草木染めに注力し始めてすぐに結果が出たわけでもないのですよ。当初関西ではまったくダメで、認めてくれたのは関東の会社ばかりでした。一社、また一社と増えて、今では40社近くなりました。有名ブランドの引き合いが多く、お陰さまで大口も増えて、右肩上がりできています。ただ、注文の大小だけで仕事を選ぶようなことはしないでおこうと思っています。長年育ててくれた取引先を後回しにするようなことはしたくありません。
—次の目標はなんでしょう。
村田社長:現在もコラボ製品は手がけていますが、いつか草木染めで、自社のオリジナルの、Made in Kyotoの最終製品をつくるのが夢です。そのほうが従業員もきっと、やりがいがあると思うのです。若い人材も加わりましたし、実現させたいですね。

特に日本の伝統色は、その名だけでも美しく、独自の精神文化すら感じられる。

蒸気の上がる工場内は、暑いときは40度にもなるそう。技術も体力も必要。

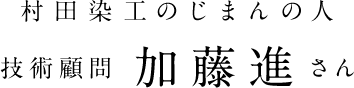

昭和14年生まれ、昭和30年入社、三代の社長を知るベテラン中のベテラン職人。平成11年の定年退職後も週3日ペースで現場で働いていらっしゃいます。村田社長曰く「努力家、勉強家」。取材時75歳!はつらつとした笑顔と受け答え、きびきびとした動き、とてもそうは見えなくてびっくりでした。
60年以上もこの業界で、染めの仕事をやってきたわけですが、そんなに長く続けてきた気はしませんね。同じことの繰り返しのようでいて、毎回違うんですよ。だからその都度一生懸命に、集中してやっているうち、こんなに年数が経っていたような感じがします。丁稚と番頭さんの時代に始めて、最初の5年は下働き。昔は社長になんか、簡単に口もきけませんでしたからね、今とはずいぶん違いますね。今はものが言いやすい。従業員同士も気心の知れた仲だから、互いに言いたいことは言いながらやってます。飲みにも行きますよ。“横のコミュニケーション”、大事でしょ。
何度やっても、色見本と同じ色に染め上げる「色合わせ」は難しいですね。難しいからこの年でもボケずに済んでる(笑)。生地によって色の乗りがぜんぜん違うし、特に天然繊維は難しい。いまだにうまくいかないこともしょっちゅうありますよ。最後の最後に頼りにするのは勘ですね。これだけは自慢できること?たいしてないけど、こんな年数働く者はいないでしょう。この先も抜かれる気がしないから、それかな(笑)。
編集後記
ご近所に、村田染工さんの染色にも使われているという名水「柳の水」の井戸があるというので、取材のあと向かいました。地下100メートルから汲み上げているというその井戸水は、くせがなくおいしいお水でした。千利休の茶の湯のほか、小野小町が化粧水にしたという記録もあるそうです。また、その井戸のある場所には、織田信長の次男・信雄のお屋敷があったとか。何気ないような街角で、そんな話が次々飛び出すあたり、さすが京都。入社63年の「じまんの人」加藤さんが、自らの歴史を「そんなに長い感じがしない」とさらりとおっしゃるのも、歴史や伝統というものが、日常の中に転がっている?場所柄があるのかもしれないと思ってしまいました。
気づけば、「キラリと光る会社」では、初回のニッカー絵具さん、番外編のトナカイさんに続き、“色”をつくり出す現場は3回目。日々、気に留めることもなくたくさんの色に囲まれて暮らしていますが、その世界は深いです。千利休と言えば、日本の伝統色には「利休色」「利久茶」「利休白茶」なんていうのも。どれも渋く、そう思って見るからでしょうか、京の粋が感じられる色です。(2015年4月取材)